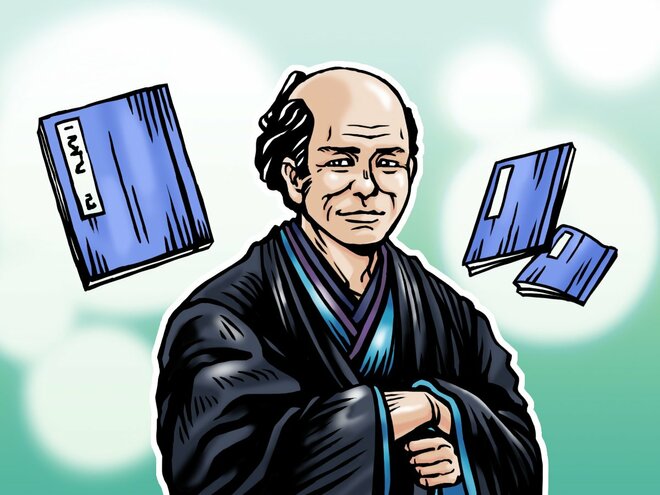教科書には載っていない“本当の歴史”――歴史研究家・跡部蛮が一級史料をもとに、日本人の9割が知らない偉人たちの裏の顔を明かす!
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の時代に狂歌が大流行した。作者らは滑稽味と社会風刺を込めた作風を競った。
『世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜もねられず』
という狂歌はこの時代を代表する作だ。幕府老中の松平定信が幕臣に文武を奨励したため、それを蚊の羽音のうるささに例えて皮肉ったもの。
この一世風靡した狂歌の陰に隠れているものの、後に狂句とも呼ばれる川柳は、実はこの時代に産声をあげた。川柳という名は生みの親、柄井(からい)八右衛門(号して川柳)の号からとったもの。その八右衛門は享保3(1718)年に江戸浅草新堀端の名主の家に生まれている。新しい文芸のジャンルを切り開いた人物ながら、なかなか商売上手な一面があった。
八右衛門の曽祖父は寛永寺の寺侍だったらしく、その関係で柄井家は代々、天台宗竜宝寺門前町(新堀端)の名主を務め、彼が38歳で父の跡を継いだ際、俳諧をたしなんでいたことから、当時、流行の兆しを見せ始めていた前句付(まえくづけ)に注目した。
庶民的で卑俗かつ滑稽味のある連歌を俳諧といい、その練習のために出題された句に付句(つけく)することを前句付という。五・七・五(発句・はっく)の17音に七・七の14音を付け、あるいは、七・七に五・七・五を付けるわけだ。元禄時代に松尾芭蕉が五・七・五の発句を、後の俳句として文学へ昇華させていったが、前句付は文芸とはいえ、あくまで庶民の言葉のお遊びだ。