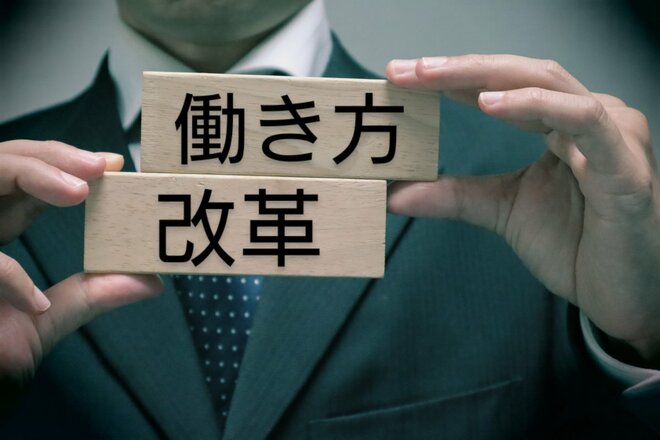日々、若者文化やトレンド事象を研究するトレンド現象ウォッチャーの戸田蒼氏が本サイトで現代のトレンドを徹底解説。今の時代に戸田氏が注目するのは働き方の大きな変化だ。
東京都をはじめとする自治体や一部企業で、週4日勤務や選択的週休3日制の導入が進み、働き方の大きな変化が現実となっています。制度導入の背景には従来の長時間労働文化を見直し、生産性と幸福度を両立させる狙いがあります。短時間勤務の導入によって従業員の生活の質が上がるだけでなく、業務効率も維持または向上する事例が国内外で報告され、社会全体の注目を集めている状況です。
東京都は2025年4月から全職員に選択的週休3日制を導入しています。給与維持型、労働時間維持型、給与減額型の3タイプを従業員が自由に選べる仕組みで、柔軟性の高さが特徴。給与維持型は週32時間労働で給与据え置き。生産性向上が前提となるため企業側の負担は大きいものの、従業員には理想的です。労働時間維持型は、1日10時間×週4日勤務で週40時間を維持し、給与も変わりません。給与減額型は、労働時間が減る分、給与が約2割カットされる仕組みです。
小池都知事が打ち出したこの施策により、週休3日制は一気に現実味を帯びてきました。すでに茨城県や千葉県など全国で12の都府県が既に導入済みで、来年1月からは愛知県と宮城県が導入予定。制度利用の流れが広がっていけば、民間でも“脱・長時間勤務”が常識となるかもしれません。
海外ではアイスランドが15年から19年にかけて、公共部門約2500人を対象に週4日勤務を実施。週40時間勤務を35〜36時間に短縮し、給与は据え置き、業務量も変わらないという条件です。その結果、ほとんどの職場で生産性は落ちず、従業員の幸福度が大幅に向上したといいます。ストレスやバーンアウト(燃え尽き症候群)が減少し、家庭生活や余暇の充実、職場環境の改善にも寄与したとされ、現在では労働人口の約90%が、実質的に週36時間勤務のスケジュールに移行しているとか。