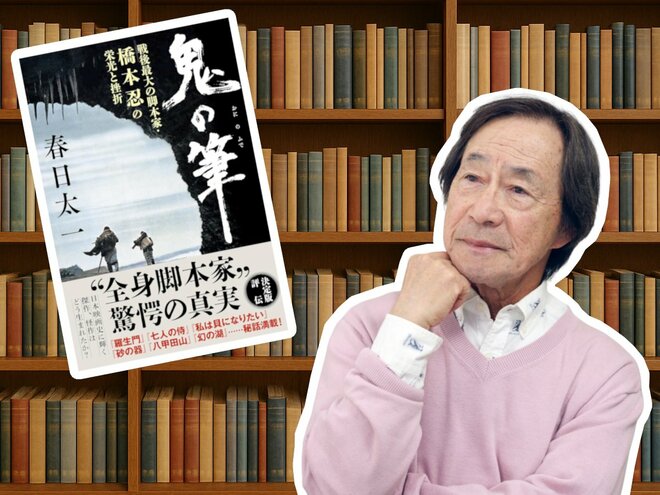武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。
稀代の脚本家・橋本忍の人生に迫った『鬼の筆』(春日太一著・文藝春秋)を題材にお話ししております。
小説を原作に、数々の名脚本を手掛けた彼ですが、本書にある言葉を借りれば、
原作の中にいい素材があれば、あとは殺して捨ててしまう。血だけが欲しいんだよ。他はいらない
というのが橋本脚本の神髄。
原作の中の「これはいい映像になる」と思える、たった一行の素材を基に、腕力でねじ伏せるが如く、観客を感動させる映画を作ってきた。
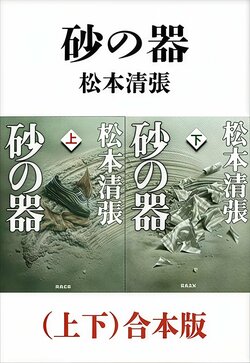
砂の器(上下)合本版(新潮文庫)Kindle版
※出典元/Amazon
その“たった一行”を映像化した究極の作品が、日本映画史に燦然と輝く不朽の名作『砂の器』(1974年公開)。
松本清張原作の『砂の器』はハンセン病という病に対する偏見と差別を取り上げ、無知な差別がどれほど人間を苦しめるのかという悲劇を描き、社会に衝撃を与えた問題作。実は映画化の話は松本清張のほうから「新聞に連載する小説(砂の器)をぜひ映画にしてほしい」と橋本に持ちかけたそうです。結局、製作開始から公開まで、実に13年もかかった――それは、なぜか?
本書には原作小説を読んだ橋本の感想が書かれています。
《いや、まことに出来が悪い。つまらん。もう生理的に読めないの。半分ぐらい読んだけど、あと読まないで、どうしようかと思ってたんだけどね……》
もう、けちょんけちょん。「面白くないから映画にならない」と橋本は思ったそうです。一方の清張は、なんとしても映画化してほしい。
そんな中、配給の『松竹』が映画化のために“虎の子の才能”を橋本に預ける。それが、若き日の山田洋次。松竹のホープで、『男はつらいよ』というヒットシリーズを持つ才能。喜劇を撮らせたら凄腕の監督で、脚本の腕も確か。聞くところによると、橋本も「洋ちゃん、洋ちゃん」と気が合ったみたいで“共同脚本”として山田洋次がスタッフに加わった。