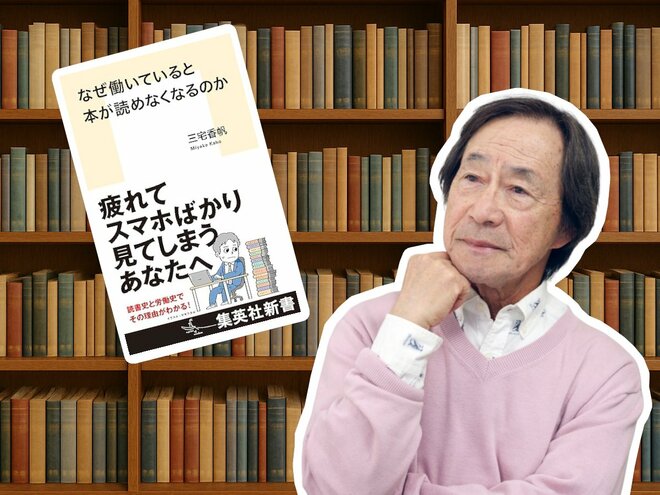武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。
1970年代、昭和40年代後半に大ベストセラーとなったのが、司馬遼太郎の『坂の上の雲』。
まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている。 ※出典:『新装版 坂の上の雲』(文春文庫)
作品はこんな一文から始まります。
明治維新から近代国家へと変貌を遂げる真っただ中の日本が、日露戦争に向かう時代に生きた3人の男を主人公に据えて、まさしく“坂の上の雲を見つめて坂を上っていく”明治という時代を描いた物語。
大ベストセラーとなりましたが、私が某出版関係者から聞いた話では「初版部数を何部にするか」で、出版元の社内は相当、揉めたそうです。「30万部にするか、40万部にするか」で揉めに揉めた結果、最終的には「40万部」という驚異の初版部数になったといいます。
現在の出版不況を考えると、「初版40万部」なんていう部数は化け物みたいな数字ですよね。まさに国民的大ベストセラー。
そして、私がすごいと思うのが『坂の上の雲』というタイトル。
大国・ロシアにも日露戦争で勝ち、坂の上の雲を掴もうと、がむしゃらに上っていった日本という国は、その先に“墜落の昭和”が待っていた。坂の下りには310万人という死者を出す日本史上最大の敗北を経験する時代があった。実は司馬遼太郎が『坂の上の雲』で伝えたかったのは、「坂を上り切ったあとの日本は落ちていったんだ」という歴史ではないだろうか。雲を目指したはいいけれど、その後は下っていくという皮肉。
折しも昭和40年代の日本といえば“高度経済成長”の時代。司馬さんの中には「高度経済成長なんて無理だろう。日本が歩んできた過去の歴史同様、いずれ転がり落ちていくんじゃないか」という、予感があったんじゃないだろうか。
以前、司馬遼太郎を担当した編集者の方と話したことがありますが、司馬先生は小説を書く際に、作中で描く現場に実際に行きたがる人だったそうです。